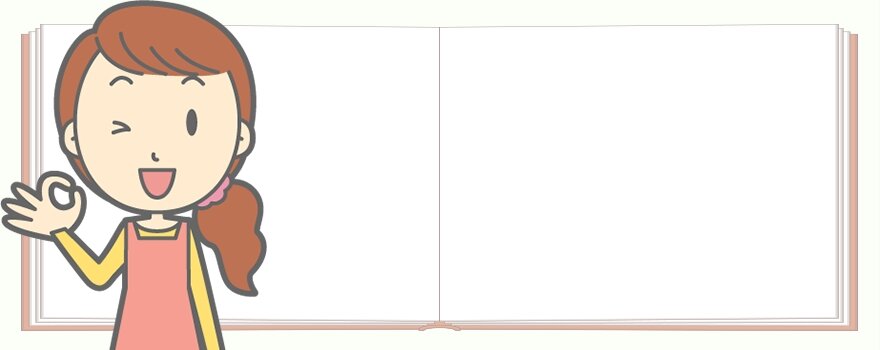仕事内容
FPで勉強する内容は、
からなります。
独立FPとして開業した場合
独立FPとして開業した場合、当然お客さんの相談内容によって使用する知識が変わるので、学習した全ての知識を総動員して相談に応じなければなりません。
保険の見直しを相談された時にはお客様の保険証書を見せてもらって保証内容を確認し、お客様が必要とする補償内容と合っているかなどを検討しないといけません。
死亡保障付の保険に入っていたが、家族も他界してしまったので死亡保障よりも医療保障の方を厚くしたい、といった要望にあった保険の検討を援助することになります。
相続の相談をされた時には、ご家族の構成を聞いて、推定相続人を割りだし、遺言書の準備を援助してあげることもあります。
相続税の計算に関しては、すでに死亡者が出て、具体的な相続税の計算が必要になった場合など、「すでに発生した具体的な相続税の計算」は税理士法に抵触するのでFPは行えませんが、将来発生するであろう相続税の仮の計算や、一般的な相続税制の説明などは可能とされています。
また、相談者の将来にわたっての人生設計の援助として、今現在得ている会社からの給料や、将来得られるであろう公的年金や民間の年金保険などの額を計算して、お客様の要望、例えば年に一回は海外旅行に行きたいので資金の準備はどうすればよいか、などの相談に答えることもあります。
銀行員として働いている場合
独立FPとならずに、例えば銀行員として働いている場合、顧客から年金や保険のことで相談を受けることもあります。

最近は銀行も保険や投資信託などの金融商品を販売しているので、お金の計算だけでなく、FPの知識が必要になる場面が多くあるのです。保険会社の従業員も、昔のようにただ保険を売っていればよいという時代ではなくなっています。
保険商品を売るからには、顧客の不安や要望を聞き、それに見合った保険商品を提示しなければなりません。そのためには保険の知識だけでなく、FPの幅広い知識が必要になります。
士業などの付帯業務では、行政書士が相続相談を受けた場合に不動産や保険の知識が必要になったりしますし、社労士が年金相談を受けた時にも同様のケースが多くみられます。
多くの場面でFP知識を活用することになるのです。